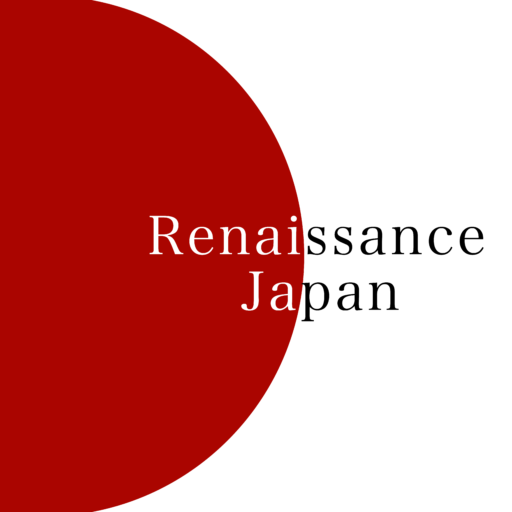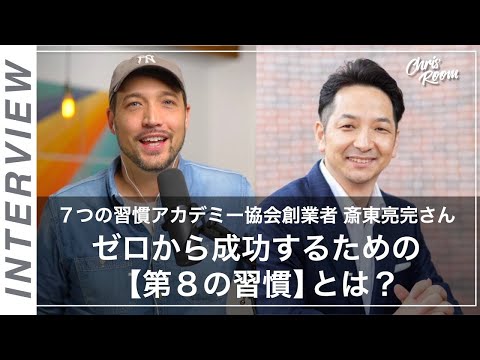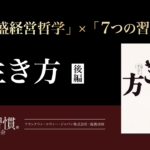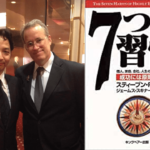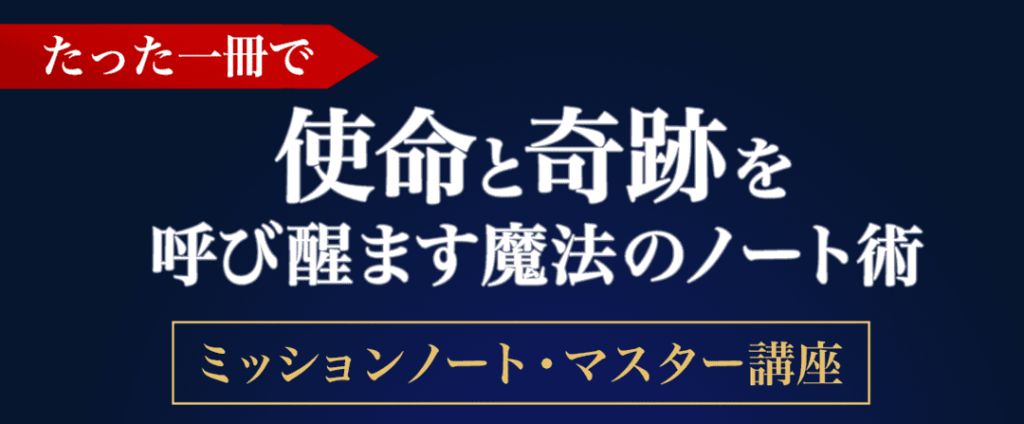『稲盛和夫の実学―経営と会計』(日本経済新聞出版)
稲盛さんが語る「会計の7大原則」。
その最初に挙げられているのが
「キャッシュベース経営の原則」です。
稲盛さんは、本書の中でこう説きます。
「お金のことを常に心配しては仕事ができない」
お金のことに気を取られ、
資金繰りに走り回っている状態では本来行うべき経営の舵取りができない。
稲盛さんはこう考えているのです。
だからこそ、ギリギリの資金繰りには決してしないようにしなくてはならない。
言い換えるならば、経営者たるもの必要に応じて使えるお金
すなわち自己資金を十分に持てるようにしなければならない
と稲盛さんは言います。
そのためには、内部留保を厚くする。
すなわち、自己資本比率を高くする。
誰かから借りてきたお金ではなく
自分の手元にあるキャッシュを蓄える。
内部留保を厚くすることが重要なのは
経営者であれば誰しも理解しているはず。
では、どうしたらそれが実現できるのか。
稲盛さんは経営者自身が
「やると決めること」から始まると言います。
そして、その教えの源泉は
あの経営の神様、松下幸之助が語ったお話から
来ているのだと言います。
稲盛さんは京セラを立ち上げた当初、
まさに資金繰りに奔走し、
自転車操業の状態にあったと言います。
その状態で、稲盛さんは
松下幸之助さんの講演会に参加し
「ダム式経営」のお話を聞きました。
ダムにたくさんの水を蓄えておき
水不足の時に放流して農作物を作るように
会社にもお金が貯まる「ダム」を
作っておくべきだ、というのが
松下幸之助さんの提唱する「ダム式経営」です。
参加者は、松下幸之助さんに尋ねました。
「どうしたら、内部留保を貯められるのか」
その問いに、松下幸之助さんはこう答えたそうです。
「その答えは、自分も知りません。
しかし、そのような余裕のある経営が必要と思わなあきまへんな」
松下幸之助さんのその答えを聞いて
多くの聴衆は笑い、真剣には捉えてない反応をしたそうです。
しかし、その多くの聴衆とは反応が異なり、
稲盛さんは、その言葉に深く心を動かされた、というのです。
何かを為そうとする時には
まず心の底から「そうしたい」と思い込まなくてはならない。
「わかってはいるけれど現実的には不可能だ」と少しでも思ったら
どんなことでも実現することはできない。
「どうしても、こうでなければならない」「何が何でもこうするのだ」という
強い意志が、経営者には必要なのだと稲盛さんは語ります。
今回は、稲盛さんが語る「キャッシュベース経営の原則」
そして
それを実現するための意志の力についてご紹介してきました。
次回は『7つの習慣』の著者であるコヴィー博士の考え方を紐解きながら
改めてこの法則についてより深く考えていきます。
■「稲盛和夫の実学―経営と会計」vol.2
鹿児島大学「稲盛アカデミー」で、生前の稲盛和夫氏から直接、指導を受ける。
その後、盛和塾所属経営者の人材育成研修会社で人材育成マネジメントに関するコンサルティング、コーチング、研修提供を10年以上担当する。
「7つの習慣アカデミー協会」代表理事・斎東亮完と出会い、法人研修講師、協会認定コンサルタントとしても活躍中。
暖かい人柄と、豊富な人材育成研修の経験から、管理職研修、新人研修などの階層別研修から、企業理念・教育制度・人事制度構築などをすすめる、「人づくり」の専門家です。

![[稲盛哲学 ×7つの習慣]「会計」は現代経営の中枢を成すもの](https://renaissance-japan.net/wp-content/uploads/2024/03/inamorifilo_10-1-300x169.png)
![[稲盛哲学 ×7つの習慣]稲盛さんも松下幸之助さんも 重要視していた共通項](https://renaissance-japan.net/wp-content/uploads/2024/03/inamorifilo_10-3-300x169.png)

![[稲盛哲学 ×7つの習慣] 従業員と「ミッション」を共有する](https://renaissance-japan.net/wp-content/uploads/2023/12/inamorifilo_07-3-150x150.png)